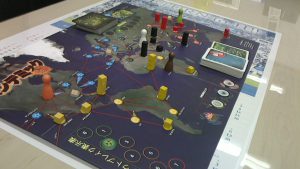先週になりますが、東京で信託実務講座を受講してきました。
この講座は、全8回で毎月1回開催されています。
今回は第6回目、テーマは「親亡きあと支援について」でした。
講義内容をざっくり書きますと、要支援者にすでに後見人が就任している場合で信託を活用する事例紹介でした。
後見と信託の併用事例は、信託の書籍でも取りあげているものは少ないそうです。
今回の講座で感じたことは、信託契約書がわかりやすく工夫されていたところでした。
信託を利用する人がわかりやすい信託契約書にするため、なるべく条文数を減らすように苦心されたようです。
あれもこれもてんこ盛りではなく、事例にあった信託契約を作成することがプロの仕事なのだなぁ、と勉強になりました(ヨシミ)
 ます。
ます。