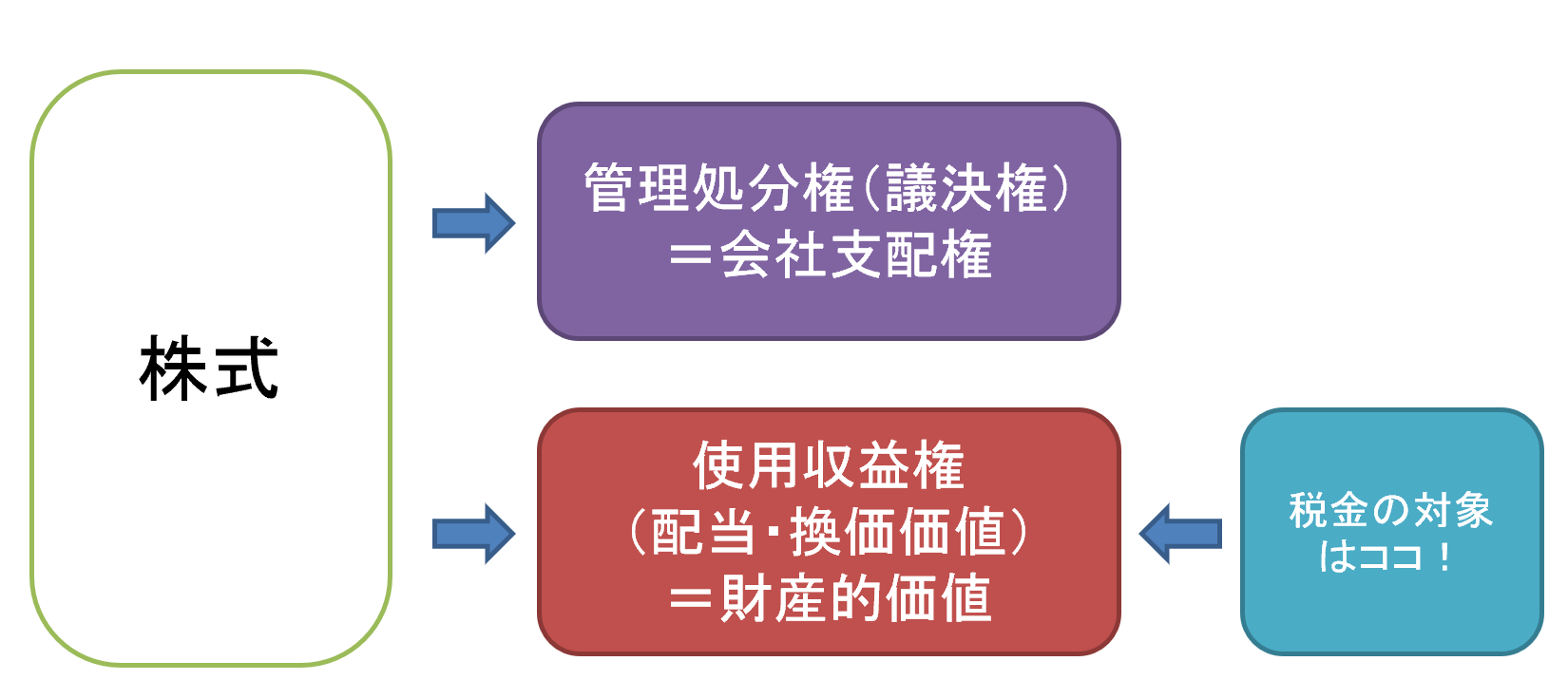先日、『民事信託をやりたいので相談したい』という方のご相談を受けました。
この方のように相談者から「『民事信託』をやりたい!」と言われるケースは最近少しずつですが増えてきました。
この方の場合、司法書士事務所を訪ねる前に、無料のセミナーで民事信託を勧められたようで、「自分たちの問題を解決するためには民事信託が適している」という認識をお持ちでした。
このような場合でも、司法書士は言われるままに信託手続きを進めることはありません。
まずはゆっくりと時間をかけて相談者の家庭の事情や様々な悩みをお伺いし、一つ一つ問題を確認していく作業が必要になります。
というのも、相談者の抱える問題が本当に民事信託で解消されるのかどうか、しっかり見極める必要があるからです。
相談者が「民事信託がいい」と言っているのに、司法書士がすぐに対応せず、事情を細々と説明しなければならないのは相談者の方にとってストレスかもしれません。
しかし、「そもそも民事信託が適しているのかどうか?」「他の解決策はないのか」という点を確認するため、必ず事情を聴くようにしています。
というのも、昨今民事信託に熱心な業者が増え、色々なセミナー、説明会、無料相談が行われているのですが、「民事信託をしておけば何でも可能」「認知症になっても家族が財産を好きに処分できるので安心」など、誤解を招く表現で説明され、まるで民事信託が万能であるかのように推奨されている場合があります。
なかには、困った事情がない方や民事信託をする必要性がない方から、「周りに『とりあえず信託しておけば困ることはない』『民事信託はいいものだ』と言われたので、とりあえず信託したい」と言われて閉口したことがあります。
無論、信託には様々なメリットがありますが、デメリットや注意点もあります。
よく説明せずに、相談者の方に言われるがままに信託した場合、かえって相談者の方の意向とは異なる結果になる可能性があります。
相談者の本当の意向に沿うため、ゆっくりと時間をかけて事情を伺ってから、ようやく伺った問題を解決するために最適な信託のスキームを提案する作業へ移ります。
相談者の方から見ると、まどろっこしいかもしれませんが、この事情聴取により、相談者の方にとっていい信託となるか否かが決まるので、お付き合いいただきたいと思います。
 から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。 うと屋内のイメージだが、ここはある種テーマパークに近い。広大な庭園の中に近現代を代表する彫刻家の名作が展示されていて、独特の雰囲気を醸し出している。足湯もあるが、待ちができるほどの混雑ぶりで、敢えてここで足湯に浸からずとも、庭園に点在する展示物を見て歩くだけで十分に楽しめる。
うと屋内のイメージだが、ここはある種テーマパークに近い。広大な庭園の中に近現代を代表する彫刻家の名作が展示されていて、独特の雰囲気を醸し出している。足湯もあるが、待ちができるほどの混雑ぶりで、敢えてここで足湯に浸からずとも、庭園に点在する展示物を見て歩くだけで十分に楽しめる。 い、うらや
い、うらや ましい気がしなくもないが、私は覚醒剤を盛られて死にたくはない。ほどほどの富とささやかな幸せが1番なのだと思う。
ましい気がしなくもないが、私は覚醒剤を盛られて死にたくはない。ほどほどの富とささやかな幸せが1番なのだと思う。 いう店の湯葉丼だ。夕方、閉店間際に訪れてもなお待ち客がいるほどの人気ぶり。正直私は湯葉はちょっと…と思っていたのだが、そんな私でも思わず「ほぅ」と感嘆してしまう。湯葉好きというちょっと変わった趣向をお持ちの同行者も大変満足されたようでほっとしている。
いう店の湯葉丼だ。夕方、閉店間際に訪れてもなお待ち客がいるほどの人気ぶり。正直私は湯葉はちょっと…と思っていたのだが、そんな私でも思わず「ほぅ」と感嘆してしまう。湯葉好きというちょっと変わった趣向をお持ちの同行者も大変満足されたようでほっとしている。 く。写真だと不気味以外の何ものでもないが、実物はもうちょっと幻想的だ。ちなみに21時半で消灯してしまう。当初計画したルートの半分も制覇してないが、想像以上に楽しいこば紀行となった。(こばやし)
く。写真だと不気味以外の何ものでもないが、実物はもうちょっと幻想的だ。ちなみに21時半で消灯してしまう。当初計画したルートの半分も制覇してないが、想像以上に楽しいこば紀行となった。(こばやし)