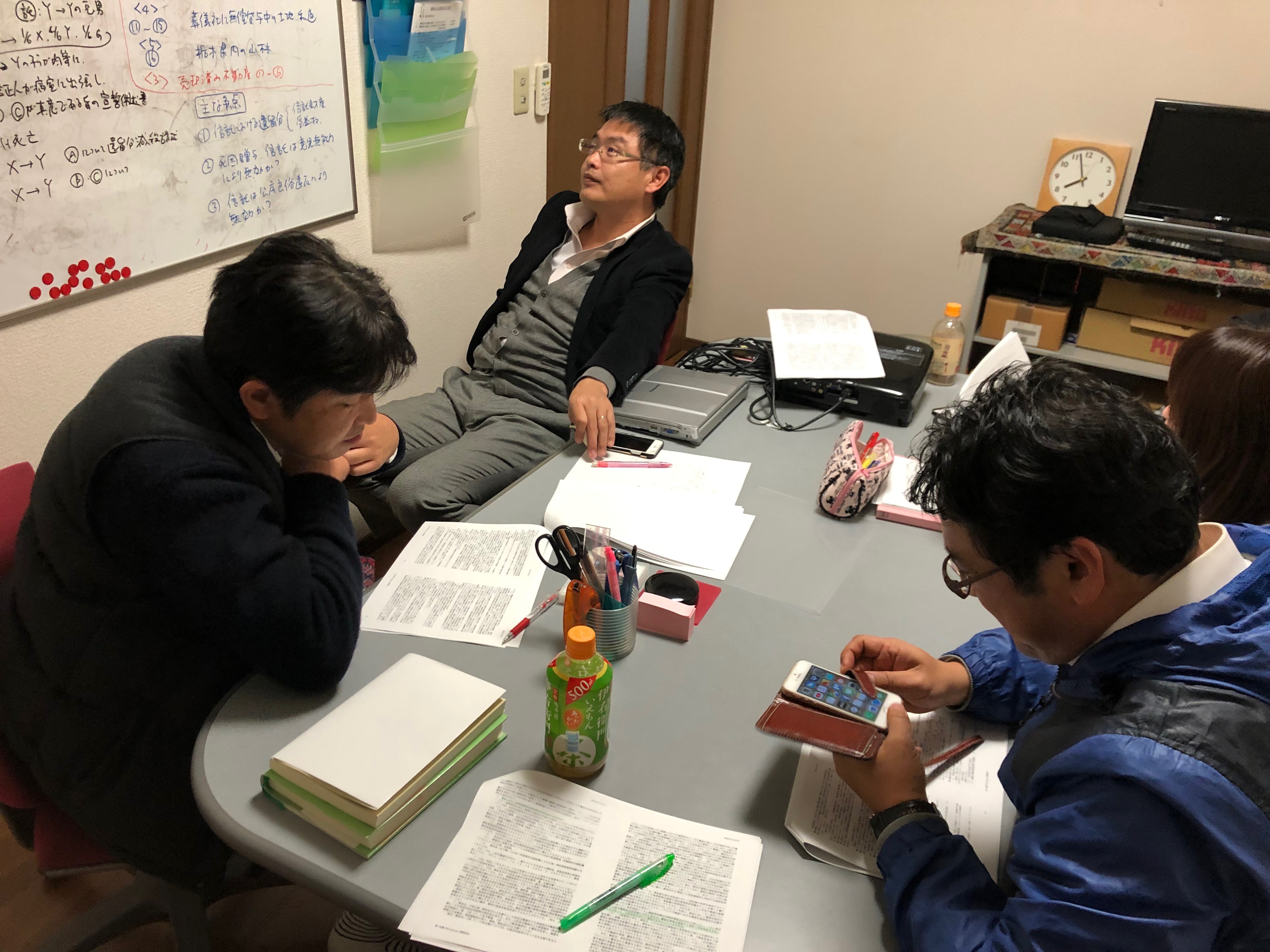本日、遺留分の放棄の相談をいただきました。
『遺留分』とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことで、兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります。
例えば、Aに妻Bと子Cがいる場合、Aさんの相続人はBとCとなり、法定相続分はBが2分の1、Cが2分の1となります。このようなケースで、Aさんが『全ての遺産は妻Bに相続させる』という遺言書を残した場合、法定相続分より遺言書が優先させるため、遺言書通りに遺産が分配されるとCは何ももらえないことになります。このような場合にCの権利を保護するため、最低限の遺産を取得できる権利が保障されております。(このケースでは、Cの遺留分は4分の1となります)
しかし、この『遺留分』は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、推定相続人が家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ放棄することができます。
Cが遺留分を放棄すれば、『全ての遺産は妻Bに相続させる』という遺言書を残した場合でも、もめることなく全てBが相続できます。
相続人にとってあまりメリットがない制度であるため、遺留分の放棄は申請すれば必ず認められるものではありません。法律で守られた遺留分という権利の放棄を無制限に認めてしまうと、財産を残す側や他の相続人の強要が行われるという恐れがあるためです。
そのようなことがないように、遺留分の放棄を行う場合には、どのような事情があって、その事情が正当かどうかということを、家庭裁判所が申立てをした本人を裁判所に呼び出し、きちんと審査することになっています。
一般的には、相当生前贈与を受けていて、遺留分をもらわなくても問題ない、というケースが多いようです。
弊所も何度かご相談はいただくのですが、申立件数がそんなに多い手続きではなく、弊所も実際に申立てたケースはありません。なので、どの程度の資料や理由付けが求められるのか手探りの状態です。
どうなることか・・・

 勢市駅から外宮までは徒歩5分程度、外宮から内宮へは路線バスのほか、直通バスが出ている。料金は400円程度、正月2日の参拝のため長蛇の列ができている。バスの順番待ちで20分、道中20分程度で目的地に到着、宇治橋→神苑→五十鈴川御手洗場→御正宮→荒祭宮…ほぼひととおり回る。普段であれば1時間程度で回りきれるのだろうが、正月なだけにそうもいかない。御正宮でお詣りするまでに40分程度は待
勢市駅から外宮までは徒歩5分程度、外宮から内宮へは路線バスのほか、直通バスが出ている。料金は400円程度、正月2日の参拝のため長蛇の列ができている。バスの順番待ちで20分、道中20分程度で目的地に到着、宇治橋→神苑→五十鈴川御手洗場→御正宮→荒祭宮…ほぼひととおり回る。普段であれば1時間程度で回りきれるのだろうが、正月なだけにそうもいかない。御正宮でお詣りするまでに40分程度は待 ったと思う。
ったと思う。 写真となってしまった。お土産は牡蠣の佃煮がおすすめである。
写真となってしまった。お土産は牡蠣の佃煮がおすすめである。