「叶(かなう)」のブログです。
ブログ
ブログ
第16条 清算受託者および権利帰属者④
(清算受託者および帰属権利者)
第16条
【再掲】
3 信託終了時の際の残余の信託財産の帰属先 は、■■■■とし、信託終了時に■■■■がすでに死亡している場合は、■■■■(住所・静岡県浜松市・・・)とする。
++++++++++++++++++++++++++++++
残余財産の帰属先を指定しておくことは、遺言と同様の効果があることをご指摘しました。とはいっても、遺言そのものではありませんので「全文・日付・氏名を自書しなければならない」というような、遺言の要式面での規制は受けません。
検討しなければならない最大の問題は、遺留分です。
遺留分とは「遺言がある場合でも最低限確保することができる遺産」とイメージしてください。
たとえば、他界した父親Xの相続人が子A・子Bだけのケース。
Xは生前に「すべてAに相続させる」とする遺言を遺していました。
この場合、Bは遺言では何の遺産も承継できないこととなります。それが故人Xの意思ですから「やむを得ない」と言えばそれまでですが、同じ子供であるA・B間での不公平感は著しいことになりますね。
そこで法律では、相続人に「遺言があっても最低限確保できる権利」を認めており、この場合のBは全遺産の25%に相当する分を、遺言によって全遺産を相続することになるAに対して請求できることとなるのです。
この遺留分の考え方が、信託の場合にも適用されると解釈されているのです。
したがって、残余財産の帰属先を指定する場合には、遺留分を考慮した指定方法を検討しておくか、あるいは遺留分の請求を受けた場合の対応方法をあらかじめ協議しておく等の準備が不可欠となるわけです。 (中里)
インフルエンザでお休みしていていました。
久しぶりにインフルエンザに罹ってしまい、1週間ほどお休みさせていただきました。
正直、結構、大変でした。
久しぶりに事務所に行ったのですが、元のペースに戻るまで少し時間がかかりそうです。
がんばります。(ななみ)
信託関係の登記で悩んでいる案件
あるお客様から所有権移転及び信託の登記がされている建物を,買い取りたいという相談を受けた。
よく話を聞けば,受託者が当該建物を買い取るのだという。利益相反とはなるものの管轄法務局とも打ち合わせて,当該買い取りに伴う登記の準備を進めていた。ところが,その買い取り代金については,金融機関の融資を受けるのだという。そうすると当該建物の土地も担保に入ることになる。お客様から,以前,土地は「私(個人)」のものですし,今回は関係ありません。と聞いていたので,金融機関から根抵当権の設定の契約書をチェックして下さいと言われるまで土地の登記については確認していなかった。
根抵当権の設定の契約書のチェックのために初めて土地の登記の情報を見て驚いた。土地は建物と同じ受託者の名義となっていたのである。
そうすると,建物の買い取りに伴い,建物は所有者であり,土地は受託者の名義となる。しかも,建物の所有者を債務者とする根抵当権の設定の登記を申請することになる。
信託目録は・・・「受託者は借入をすることができる。当該借入のために担保に供することができる」と記録されている。
では,受託者ではない者の借入のために担保に供することができるのか。
この案件は管轄法務局に照会を出している。
(文責 本木敦)
少し余談を…
ここまで遺言のお話をしてきました。今回は一休みということで別のお話をさせてください。
先日、横浜に1泊2日で財産管理についての研修を受講してきました。
講師は司法書士だけではなく、弁護士や公認会計士の方々も務めておられました。
内容自体も充実していたのですが、私が驚いたことは受講者の人数でした。会場は全て埋め尽くし開いている席が全くなかったのです。受講するには受講料がかかること、土日の研修であること等から人数もしれていると思っていたのですが、その予想は見事に外れました。しかも、参加者の熱気はものすごいものでした。どうやら、高齢者の財産管理について成年後見だけでは対応が難しいため、新たに民事信託を勉強している司法書士が増えているようです。
研修を終えて会場の外に出ると、ところどころに雪が残っていましたが、寒さを感じるよりも充実感に満たされて帰路につくことができました。(小出)
こば紀行#50 東京ラーメンストリート③
 このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。
第50回目は東京ラーメンストリート③
昨夏から定期的に東京に通っている。会議は平日の午後からなのでゆっくり観光する間もない。そこで始まった東京ラーメンストリート編、かれこれ3回を数え、今や私の中では会議よりもメインイベントだ。八重洲中央口地下、東京駅一番街、東京を代表するラーメン店8店舗がこの一角に集結。僭越ながらその1つ1つに私の極めて主観的なコメントと評点を付けさせて頂いている。
さて、今回訪れたのは「ソラノイロ」。17:20頃到着、行列ができているのは前回訪れた「六厘舎」くらいであとはどの店も並ぶことなく入店できる。ここ「ソラノイロ」も6割程度の客入りである。店内は女子の部屋みたいな小洒落た造りになっていて、客層も女子(だいぶお歳は召されてる)が多い。看板メニューは「特性ベジソバ(1,100円)」、券売機に「ここでしか食べられない!」とあったら頼むしかないだろう。
10分程でベジソバが登場、その名のとおり野菜だらけである。麺もニンジンのような色をしていてパプリカが練り込んであるんだとか。具はブロッコ リー、キャベツ、ニンジン、トマト、レンコンを揚げた物…た、確かにヘルシーである。スープもヘルシーで何と表現したら良いか分からない不思議な味を醸し出している。途中で味の変化を楽しむために柚胡椒が添えられているのだが、割と最初から全力で使った。新進気鋭の店主の、研ぎ澄まされたセンスとこだわりが感じられる一品。だが、私のような凡人には、そのセンスがあまりにも斬新過ぎて取り残された感がある。そんな私の様なお客さんのために、普通の中華そば(醤油・塩)も用意されている。
リー、キャベツ、ニンジン、トマト、レンコンを揚げた物…た、確かにヘルシーである。スープもヘルシーで何と表現したら良いか分からない不思議な味を醸し出している。途中で味の変化を楽しむために柚胡椒が添えられているのだが、割と最初から全力で使った。新進気鋭の店主の、研ぎ澄まされたセンスとこだわりが感じられる一品。だが、私のような凡人には、そのセンスがあまりにも斬新過ぎて取り残された感がある。そんな私の様なお客さんのために、普通の中華そば(醤油・塩)も用意されている。
味★ 量★ コスパ★ 中毒性★ 斬新度★★★★ 総合1.4
気を取り直して2店目、「ちよがみ」に入店。同じストリート内に ある「斑鳩」という店のセカンドブランド。東京の中華そばをコンセプトに、素材とスープにこだわっているそうだ。最もオーソドックスであろう「醤油中華そば(980円)」を注文、浜松で例えるなら有楽街の「みやひろ」を少し高級にするとこんな感じになる。求めていた安心感がここにある。ただ、Hpの店舗紹介に「日本の伝統が生み出す、至極の一杯」とあるが、作ってる従業員は皆外国人…このアンバランスさが東京独自のセンスなのだろう。
ある「斑鳩」という店のセカンドブランド。東京の中華そばをコンセプトに、素材とスープにこだわっているそうだ。最もオーソドックスであろう「醤油中華そば(980円)」を注文、浜松で例えるなら有楽街の「みやひろ」を少し高級にするとこんな感じになる。求めていた安心感がここにある。ただ、Hpの店舗紹介に「日本の伝統が生み出す、至極の一杯」とあるが、作ってる従業員は皆外国人…このアンバランスさが東京独自のセンスなのだろう。
味★★ 量★★ コスパ★★ 中毒性★★ 安心度★★★ 総合2.7
今回の東京駅で学んだこと:都会のセンスはよく分からん。
次回予告:斑鳩入店予定(3月頃) しばらくラーメンは要らん。(こばやし)
信託も色々
このサイトは民事信託(営利を目的とせず、信託銀行が取り扱う商品とは異なり、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うもの)を主に取り扱っておりますが、一言に『信託』と言っても多岐にわたり、色々な信託があります。
先日、信託銀行の商品で、『特定贈与信託』に触れる機会がありました。
『特定贈与信託』は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。
この信託を利用するメリットは、何と言っても節税効果。
特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3000万円を限度として贈与税が非課税となります。
ご家族が障害をお持ちの場合、その方の将来に不安を抱き、なるべく財産を残してあげたい、という方は多いと思います。
ただ、何の対策もせずに財産を移転してしまうと、驚くほどの税金がかかる場合がありますので、この制度は非常に有効だなと感じました。
民事信託は民事信託のメリットがあるのですが、こうった『信託』も勉強していかなければならないと感じました。
第16条 清算受託者および権利帰属者③
(清算受託者および帰属権利者)
第16条
【再掲】
3 信託終了時の際の残余の信託財産の帰属先 は、■■■■とし、信託終了時に■■■■がすでに死亡している場合は、■■■■(住所・静岡県浜松市・・・)とする。
++++++++++++++++++++++++++++++
前回は信託終了時の財産の帰属について概説しました。
皆さん、今日のブログを読み進める前に、再度前回の投稿に目を通してみてください。何かにお気づきになるのではないかと思います・・・
「まるで遺言みたい」と感じた方も少なくないのではないでしょうか?
そうなんです。信託は、必ずしも委託者の死亡によって終了するパターンばかりではありませんが、委託者の死亡が信託終了事由である場合、信託終了時の残された信託財産は、委託者の「遺産」と同視できそうですね。
もっとも、委託者の生前に受託者に所有権が移ってしまっているわけですから、厳密には「遺産」ではありません。しかし、信託契約の際にあらかじめ死亡(=信託終了)時の財産の帰属先を指定しておくことにより、あたかも「遺言」を書いたのと同様の効果を生じさせることができますし、清算受託者は、遺言執行者と同様の役割を担うことになるわけです。
したがって、この条項の起案にあたっては、委託者の真意を十分に理解しなければなりません。また、遺言と同様の効果があるという点から、一定の法的規制も発生します。この点は次回に! (中里)
掛川支部の会員研修の講師としてお招きいただきました!
先日、民事信託グループ「叶」が静岡県司法書士会掛川支部会員研修会の講師としてお招きいただきました!
内容は次のとおりです。3月10日は、浜松支部でもお招きいただいています!
第1講‥「信託の基礎と受任時における聞き取り方法~「
第2項‥「契約条項から信託目録を起案してみよう」(中里 功)
第3項‥「信託実務の盲点」(名波直紀)
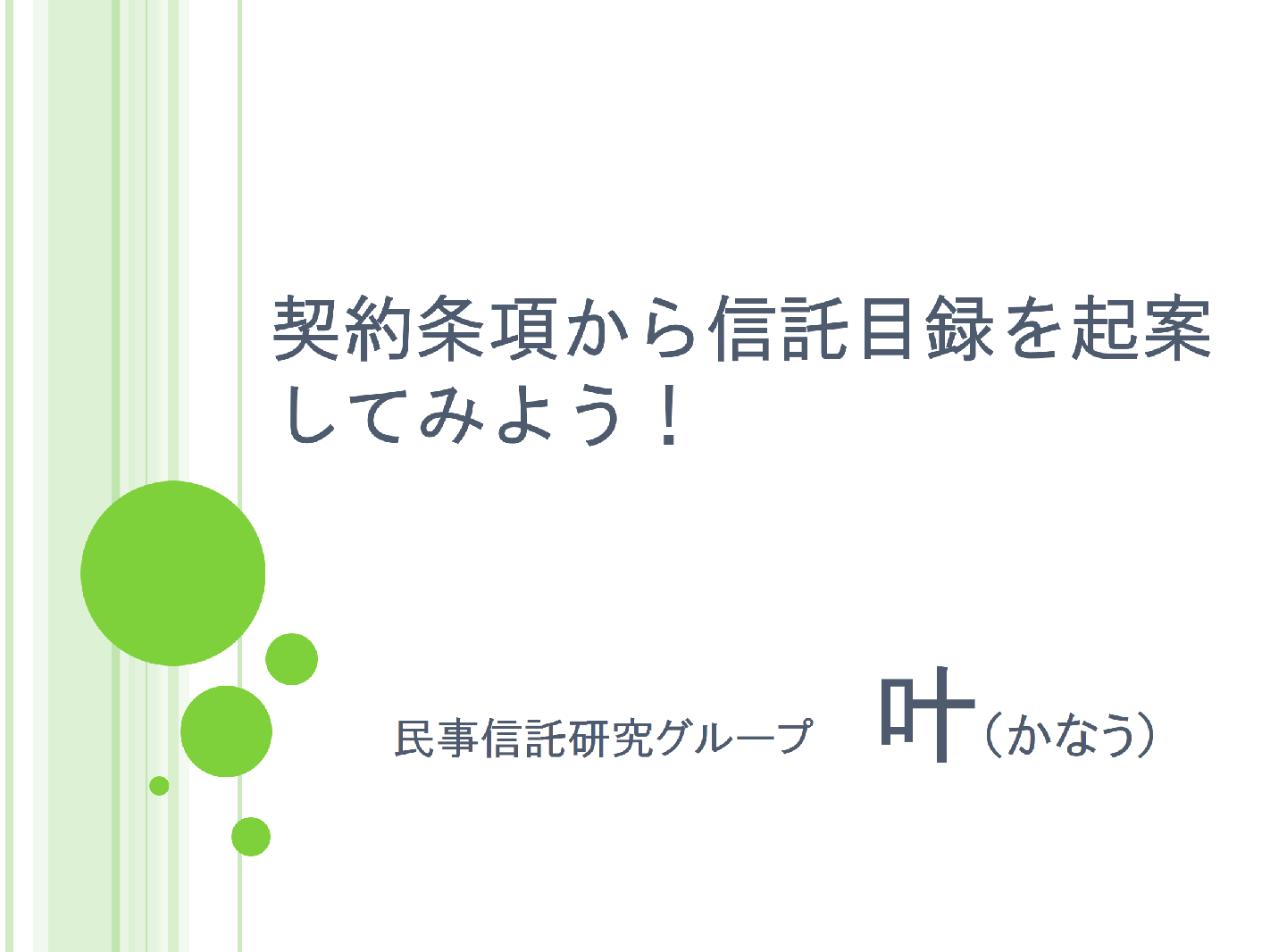
However, I had never been aware of everyone ‘s acquiring a genuine dissertation released in that way that was nontraditional.
If you are thinking about taking the check you’re currently even. This may create the variation on an essential issue on the check. On-line GED assessments were developed in these way that consumers can attempt personal segments at one time or just take the whole test at exactly the same go. Whether at a course with support from free net GED testing, or with self – study, these trial tests will offer you an idea about how ready you’re for this test. (さらに…)
ゴートゥカトマンズ(3)
2000年3月の上海は今とは違ったと思う。
外灘は現在のような近代的なものではなかった。豫園商城では小籠包を食しながら歩いたと思う。小籠包の売店では,年頃の女性が働いていた。家族経営なのだろうか,表情は明るかった。これだけ観光客が集まってくれば,売れないことはないだろう。作れば売れる。儲かる。忙しそうだった。
中国は当然のことながら外国であり,言葉の壁はあった。英語は殆ど通じない。一部の大卒の方だけが英語で会話できるという感じ。私も英語は得意ではなかったが,中国人も私も英語は話し言葉で会話するので,まだ意思疎通し易かった。片方がネイティブだと省略形だったり,訛りがあり聞き取ることができないからだ。もっとも,中国人と会話するときは最後は筆談ができ,漢字を示すとだいたい意味が分かる。やはり漢字は便利だと感じた。
NTは大学で中国語を履修しており片言の言葉を教えてもらったが,一番役に立ったのはやはり,「ツーソーツァイナール」であろう。
便所はどこにあるかという意味なのだが,当時の中国のトイレは探すのがとても大変だった。有料でもあるので財布は必須だった。
トイレはそんなに綺麗ではなかったが十分に用は足せた。
実は私は上海が初めての異国の地だった。初めての外国。気分は高揚していた。
(続く)文責本木敦